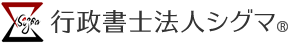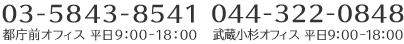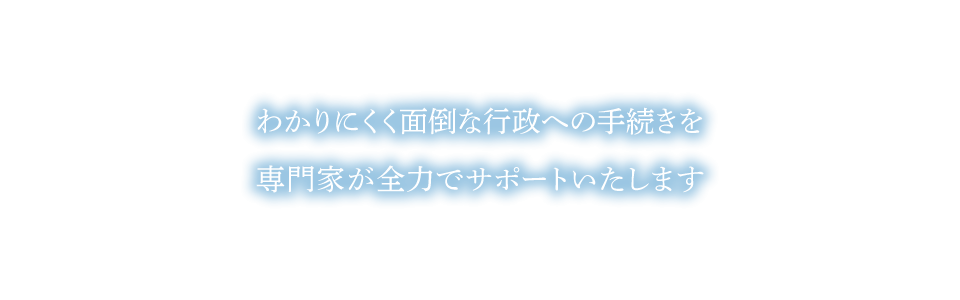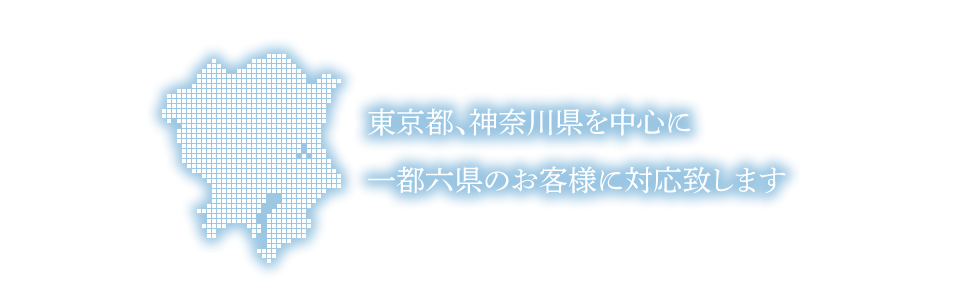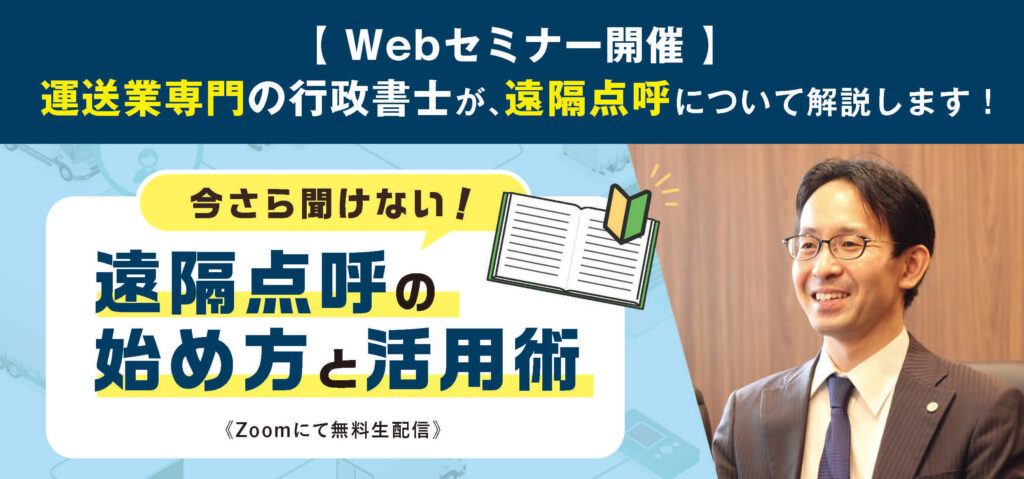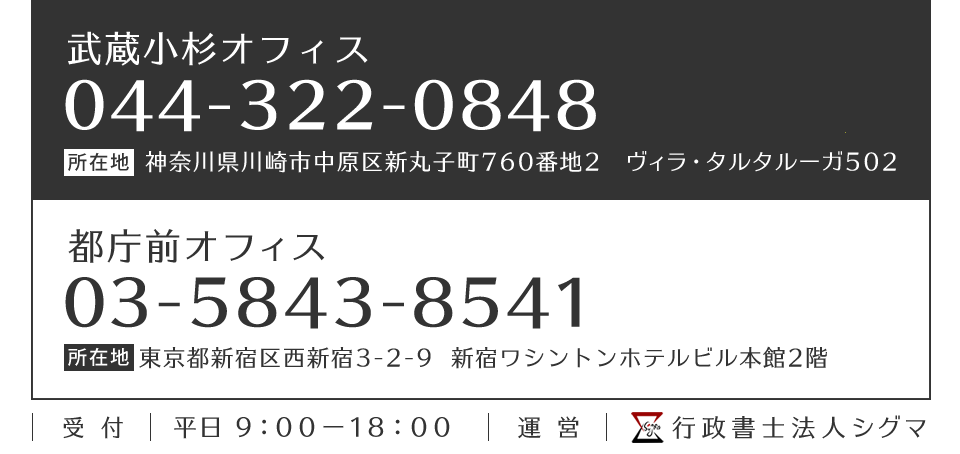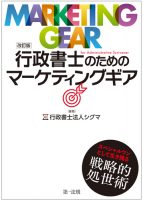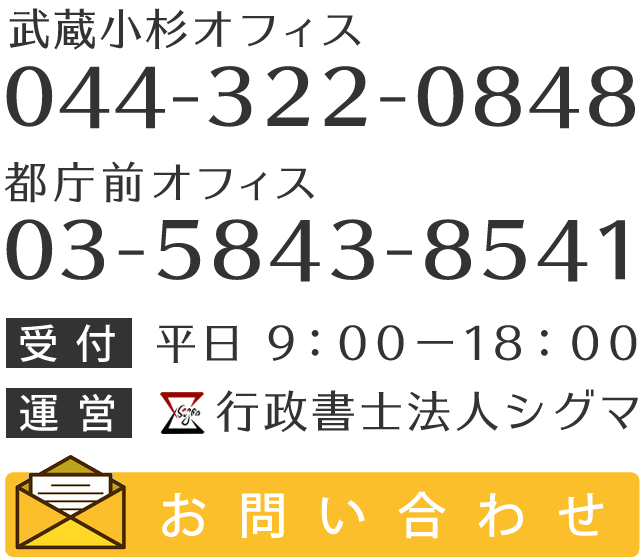2024年4月1日に施行された遠隔制度の改正情報はこちらをご参照ください。
※本ページは、2023年7月1日時点の情報で執筆しております。
2022年4月1日から始まった遠隔点呼制度。
遠隔点呼制度が始まる前は、Gマーク認定を取得していたり、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所ではIT点呼を認められていました。
遠隔点呼は、新しい点呼執行方法として注目を浴びました。
そして、国土交通省は1年間にわたる遠隔点呼の実施状況を踏まえて、2023年4月1日より新しい遠隔点呼制度がはじまりました。
2023年3月31日までは「遠隔点呼実施要領」に基づいて運用されていた遠隔点呼ですが、2023年4月1日からは、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(国土交通省告示第 266 号)」に基づいて運用されています。
そこで、このページでは2023年4月1日より変更になった遠隔点呼制度について、行政書士の阪本浩毅が解説いたします。
遠隔点呼とは
遠隔点呼の定義は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(国土交通省告示第 266 号)に記載されています。
『旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、 遠隔の営業所又は車庫にいる 運転者に対して行う点呼をいう。』
遠隔点呼に対応している機器を使って、遠隔の営業所や車庫にいる運転者に対して行う点呼のことを、遠隔点呼と呼びます。
遠隔点呼と業務後自動点呼の違い
遠隔点呼のご説明をすると、ロボット点呼との違いについてご質問いただくことがありますが、遠隔点呼とロボット点呼は全く別の点呼執行方法です。ロボット点呼の正式名称は、業務後自動点呼です。
業務後自動点呼は、事業者が機器を使って、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対して行う点呼のことを言います。業務後自動点呼は、遠隔にはいない乗務を終了した運転者に対して、事業者の営業所又は車庫において行う点呼を自動化する点呼執行方法です。
遠隔点呼が実施可能な範囲
遠隔点呼は、遠隔の営業所や車庫にいる運転者に対して、機器を使用して行う点呼であるとご説明いたしました。
それでは、遠隔の営業所や車庫であれば、無制限に遠隔点呼を実施できるのでしょうか。答えは「ノー」です。
遠隔点呼が実施できる2地点間は告示で以下の8つのパターンのみであると規定されています。
- 自社営業所と当該営業所内の車庫との間
- 自社営業所の車庫と当該営業所内の他の車庫との間
- 自社営業所と他の自社営業所との間
- 自社営業所と他の自社営業所内の車庫との間
- 自社営業所内の車庫と他の自社営業所内の車庫との間
- 自社営業所と完全子会社等の営業所との間
- 自社営業所と完全子会社等の営業所内の車庫との間
- 自社営業所内の車庫と完全子会社等の営業所内の車庫との間
8つのパターンのうち、1.~5.は、自社のなかでの遠隔点呼が実施できる2地点間になります。
6.~8.は、自社の営業所以外において、遠隔点呼が実施できる2地点間になります。
完全子会社等について解説いたします。完全子会社等とは、法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社(完全子会社)と、会社を完全子会社とする他の会社、事業者と完全親会社が同一である他の会社のことです。
いわゆる孫会社であっても完全子会社とみなす規定はありますが、ここでの説明は割愛いたします。
事業者と完全親会社が同一である他の会社とは、ホールディングス内の別会社をイメージして頂ければご理解いただけるかと思います。
自社内ではなく他社の営業所や車庫において遠隔点呼が実施できるかどうか悩ましいときは、遠隔点呼の相手側の株主名と持株数が記載されている資料をご準備の上、営業所を管轄する運輸支局に事前相談されるのがよいでしょう。
遠隔点呼を実施するための要件
遠隔点呼を実施するためには、大きく分けて3つグループに分類されている要件を満たさなければなりません。
3つのグループとは、次のように分類されています。
- 遠隔点呼機器の要件
- 遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件
- 遠隔点呼機器の運用上の遵守事項
これらの3要件は、遠隔点呼が対面による点呼と同等の効果を有するものであるために規定されております。
細かい要件については、各グループごとに次のようになっています。
1.遠隔点呼機器の要件(11項目)
1つ目のグループの要件は、点呼執行者(運行管理者又は補助者)と運転者が点呼執行の際に使用する機器のスペックの要件です。
| 要件 | 適・否 | |
| 1. | 遠隔点呼を行う運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる機能を有すること。 イ 運転者等の顔の表情 ロ 運転者等の全身 ハ 運転者の酒気帯びの有無 ニ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 |
|
| 2. | 運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度を自動的に記録及び保存するとともに、遠隔点呼を行う運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる機能を有すること。 | |
| 3. | 遠隔点呼を行う運行管理者等及び遠隔点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法により確実に個人を識別する機能を有すること。 | |
| 4. | 次のイからトまでに掲げる事項が遠隔点呼実施地点間で共有され、当該事項について遠隔点呼時に遠隔点呼を行う運行管理者等が確認できる機能を有すること。 イ 運転者等の日常の健康状態 ロ 運転者等の労働時間 ハ 運転者等に対する指導監督の記録 ニ 運行に要する携行品(以下単に「携行品」という。) ホ 乗務員等台帳の内容 ヘ 運転者等に対する過去の点呼記録 ト 運行に使用する事業用自動車の整備状況 |
|
| 5. | 点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平常時と比較して確認できる機能を有すること。 | |
| 6. | 点呼を行う運行管理者等が、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果を確認できる機能を有すること。 | |
| 7. | 遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等に伝達すべき事項を確認できる機能を有すること | |
| 8. | 遠隔点呼を受けた運転者等ごとに、次のイ及びロに掲げる事項を電磁的方法により記録し、遠隔点呼実施地点間で共有するとともに、その記録を一年間保存する機能を有すること。
イ 業務前の遠隔点呼に係る事項 ロ 業務後の遠隔点呼に係る事項 |
|
| 9. | 遠隔点呼機器の故障が発生した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。 | |
| 10. | 電磁的方法により記録された項目八に掲げる事項及び項目九の記録の修正若しくは消去ができないこと又は電磁的方法により記録された項目八に掲げる事項及び項目九の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去ができない機能を有すること。 | |
| 11. | 電磁的方法により記録された項目八(イ(7)及びロ(7)を除く。)に掲げる事項及び項目九の記録について、遠隔点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。 |
3番目の項目では、点呼執行者側・運転者側の双方が生体認証機能を使ったなりすまし防止機能が要求されています。
9番目の項目では、遠隔点呼機器が万が一故障した場合に、故障発生日時と故障内容を自動的に記録することと、故障記録を1年間保存する機能が要求されています。
10番目の項目では、遠隔点呼の記録について改ざんできないこと、改ざんが行われたときは、修正前の情報が上書きされずに履歴が残りことまでが要求されています。
2.遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件(4項目)
2つ目のグループは、1番目のグループで定義されている遠隔点呼機器を設置する場所、いわゆる点呼場がどのような条件である必要かを規定しています。
| 要件 | 適・否 | |
| 1. | 遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。 イ 運転者等の顔の表情 ロ 運転者等の全身 ハ 運転者の酒気帯びの有無 ニ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安 全な運転をすることができないおそれの有無 |
|
| 2. | なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び所定の場所以外での遠隔点呼の実施を防止するため、遠隔点呼実施場所の天井等に監視カメラを備え、運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等の全身を随時、明瞭に確認することができること。 | |
| 3. | 遠隔点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。 | |
| 4. | 遠隔点呼を行う運行管理者等と遠隔点呼を受ける運転者等との対話が妨げられないようにするために必要な通話環境が確保されていること。 |
遠隔にいる運転者の点呼場は、運転者の表情や全身が確認できる明るさ(照度)が確保され、運転者のなりすまし防ぐために、運転者の全身をリアルタイムで確認できるカメラが必要になります。遠隔点呼機器を作動させるための電源やインターネット接続環境も当然求められますので、運転者側の点呼場の整備が遠隔点呼の導入の障害になるのではと考えております。
3.遠隔点呼機器の運用上の遵守事項(10項目)
最後のグループには、遠隔点呼制度を導入後のルールについて規定されています。
| 要件 | 適・否 | |
| 1. | 遠隔点呼を行う運行管理者等は、地理情報及び道路交通情報等、事業用自動車の運行の業務を遂行するために必要な情報を有すること。 | |
| 2. | 遠隔点呼を行う運行管理者等は、面識のない運転者等に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ当該運転者等と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談する機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。 イ 運転者等の顔の表情 ロ 運転者にあっては、健康状態 ハ 運転者にあっては、適性診断の受診の結果 ニ その他遠隔点呼を実施するために必要な事項 |
|
| 3. | 遠隔点呼を行う運行管理者等は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の事業用自動車の位置の把握に努めること。 | |
| 4. | 遠隔点呼を行う運行管理者等は、遠隔点呼を受ける運転者等の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。 | |
| 5. | 遠隔点呼を行う運行管理者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者等が所属する営業所の運行管理者等に連絡すること。 | |
| 6. | 第五項の場合にあっては、事業者は、遠隔点呼を行う運行管理者が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した運転者等の所属する営業所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。 | |
| 7. | 遠隔点呼機器の故障等により遠隔点呼を行うことが困難になった場合にあっては、遠隔点呼を受ける運転者等が所属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の当該営業所で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。 | |
| 8. | 完全子会社等との間で遠隔点呼を行う場合は、必要に応じ、事業者及び完全子会社等の間において、遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結すること。 | |
| 9. | 事業者は、運行管理者等及び運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ対象者から同意を得ること。 | |
| 10. | 事業者は、遠隔点呼の実施に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記するとともに、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。 |
掲げられている10個の運用上の遵守事項の中には、努力義務のものと義務のものが混ざっているので、誤った解釈をしないように注意が必要でしょう。
遠隔点呼をはじめるための行政手続き
遠隔点呼をはじめるときは、「遠隔点呼の実施に係る届出書」を遠隔点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局に提出いたします。
提出する運輸支局は、遠隔点呼実施側と被実施側の双方に提出する必要があります。例えば、東京にある営業所と神奈川にある営業所の2地点間で遠隔点呼を実施する場合は、東京運輸支局と神奈川運輸支局のどちらの運輸支局にも届出書を提出する必要があるのです。
この届出書の提出時期は、遠隔点呼を実施予定日の10日前に提出となっています。事後届出ではなく事前届出である点が注意が必要です。
届出書は、旅客と貨物では届出書の様式が異なっています。
届出書に添付する書類の1つ目は、「点呼機器・システムのパンフレット等、性能及び機能が確認できる書類」です。
パンフレットに加えて、点呼執行者側・運転者側にぞれぞれどのような遠隔点呼機器が配置されているかがわかるよう、配置状況がわかる写真を提出することにより、運輸支局への開始届出手続きが円滑に進むものだと考えています。
また、自社内の営業所・車庫の2地点間ではなく、完全親会社・完全子会社・グループ会社間といった別の事業者間で遠隔点呼を実施したい場合は、完全子会社等であることを示す書類が必要になります。
完全子会社等であることを示す書類は、具体的には、毎事業年度の経過後100日以内に運輸支局へ提出する事業報告書の第1号様式のコピーが該当いたします。
そして、遠隔点呼を実施後に変更が生じた場合や、遠隔点呼を終了するときも、営業所を管轄する運輸支局への行政手続きが必要になります。
遠隔点呼を導入する利点と課題
遠隔点呼を導入する利点は、営業所と車庫は離れている場合は、点呼のために点呼執行者や運転者の移動時間を削減できます。
ご存知のとおり、2024年4月より、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されます。
運転者の拘束時間の削減を行うためには、遠隔点呼を導入することで、点呼を受けるための移動時間を削減することが可能になります。
また、運転者と同様に、点呼執行側の運行管理者や補助者も長時間労働になりがちです。
一営業所に複数の点呼執行者が在籍していれば、早番・遅番のローテーションを組むことで対応することができますが、運転者と同様に、点呼執行者側の人材確保も大変な状況だと伺っております。自社の他営業所や、完全子会社・完全親会社・ホールディングス内のグループ会社の営業所間で、運転者への点呼執行業務を分担できるのば遠隔点呼を導入する利点と言えるでしょう。特に早朝や深夜の時間帯の点呼執行業務の負担を軽減できるでしょう。
一方で、遠隔点呼を導入する課題としては、遠隔点呼制度に対応した機器の準備や社内体制の整備があります。遠隔点呼機器やなりすまし防止のための監視カメラに関しては、遠隔点呼に対応した機器のメーカーや販売店に相談することで解決できるものだと考えております。
乗務前点呼・乗務後点呼は、運転者とのコミュニケーションや、事故防止教育の場でもあります。
映像と音声をリアルタイムでつなぐことで点呼執行者と運転者が双方向でコミュニケーションを取ることはできますが、対面の方が、きめ細かなコミュニケーションが取れます。
運転者との対面でのコミュニケーションが減ることで事故が増えないように、乗務員教育の方法も工夫が必要になるのではないでしょうか。
なお、遠隔点呼制度の導入することで、非実施側の営業所においても、引き続き、運行管理者の選任は必要になります。
運行管理者の選任ルールは従前どおりです。
終わりに
2023年4月1日より、遠隔点呼制度は「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(国土交通省告示第 266 号)」に基づいて運用されています。
運用ルールが変更したことにより、遠隔点呼をはじめるための要件が告示に記載されましたが、要求される3つの要件「遠隔点呼機器の要件」「遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件」「遠隔点呼機器の運用上の遵守事項」は、表現方法は変わりましたが、2023年3月31日までの要件と本質的な変更はないと言えるでしょう。
一方で、遠隔点呼をはじめるための行政手続きは簡素化したと言えます。2023年3月31日以前は、運行管理高度化検討会の承認が必要でしたら、その承認は不要になりました。運行管理高度化検討会の承認にあたって、管轄運輸支局により現地調査が実施されておりましたが、現地調査は原則、行わない運用に変更されております。
今後は、運行管理高度化検討会の事前確認制から、法令遵守体制を確認する巡回指導・監査の事後確認制の下で、遠隔点呼制度は運用されることになったと考えております。
※本ページは、2023年7月1日時点の情報で執筆しております。
文:阪本浩毅(行政書士)
遠隔点呼に関するセミナー情報
2023年7月12日~14日 セーフィー株式会社様・テレニシ株式会社様が共催された遠隔点呼をテーマにしたウェビナーに、当法人代表の阪本行政書士が登壇いたしました。